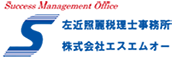3月になって暖かい日が増え、春の陽気をいっぱい感じる今日この頃ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。確定申告では大変お世話になりありがとうございます。この場をおかりして改めて御礼申し上げます。今回は、どこの本屋にでも平積みさている「識学」の安藤広大さんの「パーフェクトな意思決定」(ダイヤモンド社)、以前に買ってしばらく積読になっておりましたが、本書から印象に残りましたところを引用ご紹介させていただきます。
〇意思決定というと、「固い意志をもつこと」のように思われる。それは違う。むしろ逆だ。意思決定は「石のように固いもの」などではない。「石」より「水」に近いイメージだ。 水というのは、時に「固い氷」にもなり、「柔らかい水」に戻ることもできる。とてもしなやかな存在だ。そんな水のようなスタンスが、意思決定の本来の姿である。
本当に優秀な人は、「間違えたことを認める」ことができる。人は間違える、この世に常に正しい人はいない。人は時間とともに考えを変える。水のようなしなやかな意思決定こそが大事なのだ。「意見を変える人」は、弱そうに見える。けれど実は強い。
〇「絶対的に正しい意見はない」「つねに正解を出し続ける天才はいない」ということ。そういう前提で組織の土壌をつくっていきましょう。
仮説を立て、検証し、失敗を認め、修正する。そのとき、「誰も個人を責めない土壌」が必要です。「パーフェクトな意思決定」というのは、そうやって変化に対応していくことが前提となります。だから、「朝令暮改」という言葉を当然とするのです。
〇「やってみないとわからない」という不確実性が大いにあります。そんな中でも、いち早く決定して、少しでも早く、チームを勝利に導くことがリーダーの責任です。結果的に勝利に導く、ということです。そのためなら、失敗や修正は必要です。100%正しい意志決定をし続けることは不可能です。ただし決めたことは全力でやる。その結果、修正が必要になったとき、自分の失敗、自分に都合の悪いことでも、受け入れて修正できるかどうか。組織全体を停滞させず、「結果的にうまくいくことに貢献した意思決定」を「パーフェクトな意思決定」と呼んでいます。
〇意思決定をしないといけない問題や課題を3つの箱にいれておくようにしましょう。
一つ目、すでに十分な情報があるとき、「即決」という箱にいれて、その場で決めるようにしましょう。二つ目、意思決定の難易度が高めの問題で、意志決定をするための情報が不十分なときは、「情報不足」という箱にいれて、どういう情報が必要なのか明らかにして判断材料を集めます。三つ目、意思決定をするための情報として、もう少し時間をかけて経過をみたいというとき、「期限を設定する」という箱にいれて期限を設定することが大事です。
〇会議においては、意思決定者を決めて、意思決定者が決める。
全員の納得を得ようとすることはムダなことです。決定的な事実があるわけではなくて、感想レベルのノイズは、相手を説得しようとしないというスタンスでスルーする。自分がむきあうべき「事実」だけを見て、自分が変えられることに取り組む。
〇重大な意思決定をするときは、その前に一呼吸、「自分の感情を整理すること」をしましょう。また、反対意見を言われると、つい感情がでてしまいますね。 「15分、30分、1時間…。一人きりで考える時間を作る」ということです。原始的ですがそれしか方法はありません。そして、理論的に判断する。ゆっくりと冷静に決める。ただそれだけです。
〇意思決定において重要なのは、「賛成する人の人数」や「全員の同意」ではありません。責任に応じて意思決定をし、結果を出すことこそが正義なのです。
できるだけ客観的な事実を集める、メリットとデメリットを比べる。どちらが大きいのかを決める。 そして、最後の最後は「勇気」しかない。
「決めたことを実行して、何とか成功に持っていくしかない」という真理に達するのです。
以上、本書にある安藤さんの言葉を紹介引用させていただきました。安藤さんの提唱される「識学」全般、規模の小さい会社でそのままとりいれるのは難しいと思っていましたが、今回またいろいろなことを考えさせてもらいました。
その時その時の状況に応じて、情報を集めて、試行錯誤を繰り返していって。最後は勇気。少しでもよかったと思えるようにしていきたいと思った今日この頃でした。
参考文献:「パーフェクトな意思決定」 (ダイヤモンド社 著者 安藤広大)